
ラヴィ教習所がお届けする、交通安全にまつわるコラムです。
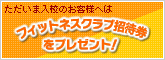
入校のお客様はラヴィセントラルフィットネスクラブ蒲田の招待券をプレゼント!
|

|



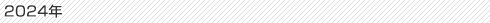

●
|
2024年11月1日施行
道路交通法が改正され、令和6年(2024年)11月から自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化され、また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされました。自転車の酒気帯び運転に関しては、運転をした本人はもちろん、酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した者等、酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が科されます。
自転車運転中の「ながらスマホ」
自転車運転中、停止している間を除いて、スマホで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されました。なお、スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。
酒気帯び運転及び幇助
\飲酒して自転車を運転することは禁止されており、これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、今般の道交法改正により「酒気帯び運転」(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること)についても罰則の対象となります。また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止です。
|
罰則 |
自転車運転中の
「ながらスマホ」 |
違反者
|
6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金 |
交通の危険を
生じさせた場合 |
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
酒気帯び運転
及び幇助 |
違反者・自転車の
提供者 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
酒類の提供者
・同乗者 |
2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
出典:政府広報オンライン
警視庁

|

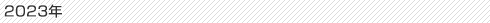

●
|
2023年7月1日施行
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定
車体の大きさや構造等が一定の基準に該当する原動機付自転車が「特定小型原動機付自転車」とされました。
特定小型原動機付自転車による交通違反は交通反則通告制度および放置違反金制度の対象とされ、危険な違反行為を繰り返す者には講習の受講が義務づけられました。
|
改正前 |
特定小型原付(改正後) |
特例特定小型原付(改正後) |
| 運転免許 |
必要 |
不要 |
不要 |
| ヘルメット |
必要 |
努力義務 |
努力義務 |
| 自賠責保険 |
必要 |
必要 |
必要 |
| ナンバープレート |
必要 |
必要 |
必要 |
| 速度制限 |
時速30km |
時速20km |
時速6km |
| 走行可能な場所 |
車道 |
車道・路側帯・自転車道 |
歩道・路側帯 |
| 年齢制限 |
免許に準ずる |
16歳以上 |
16歳以上 |
| 最高速度表示灯 |
- |
緑色点灯 |
緑色点滅 |

|
●
|
2023年5月13日施行
75歳以上の免許更新手続について以下の3点が改正
高齢運転者対策の充実・強化をはかるため75歳以上の免許更新手続きについて以下の3点が改正されます。
1.認知機能検査の検査方法の変更
2.高齢者講習の一元化
3.運転技能検査の新設
原付、二輪、小型特殊、大型特殊だけの運転免許をお持ちの方及び運転技能検査に合格した方は実車指導なしの1時間講習になります。
運転技能検査とは、75歳以上の高齢運転者のうち、普通自動車対応免許の方が一定の違反行為をした場合、免許更新時等に運転技能検査の受検が義務付けられ、運転技能検査に合格しない場合は運転免許の更新はできません。
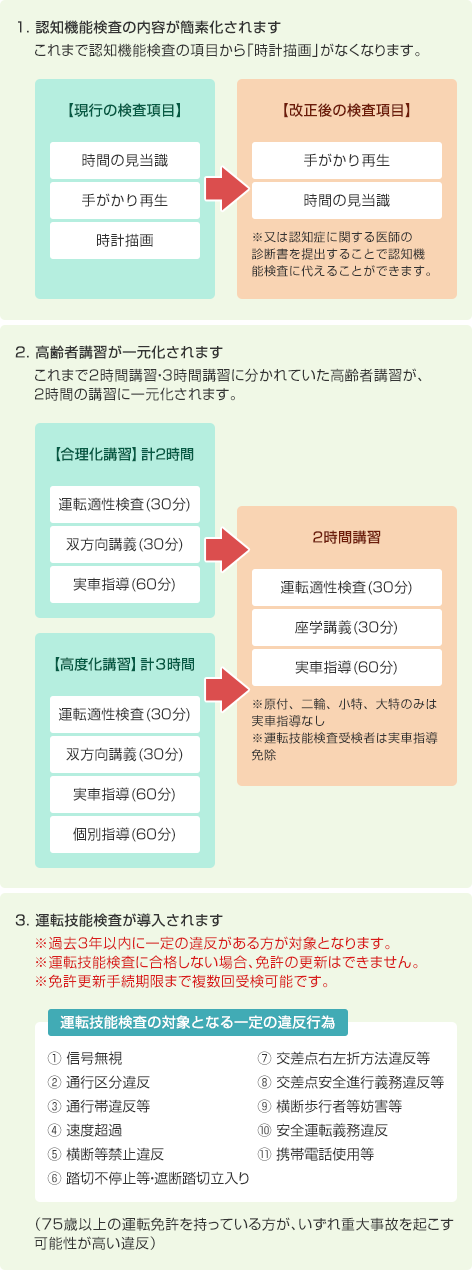

|
●
|
2023年4月1日施行
自転車乗車時のヘルメット着用努力義務
自転車に乗るときも全員にヘルメットの着用が努力義務として課せられることになりました。自転車乗車時のヘルメット着用は2008年に実施された改正道交法で、13歳未満の児童や幼児が乗るときに被らせるように保護者への努力義務が定められましたが、新たな改正道交法では、2023年4月1日以降、自転車に運転する人全員に対象を広げ「被るように努めなければならない」という規定になりました。
(道路交通法第63条の11)
第1項:自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
第2項:自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
第3項:児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
|

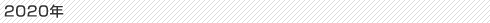

●
|
2020年6月30日施行
妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則の創設
東名高速道路等で起こった交通死亡事故等をきっかけに「あおり運転」が社会問題化したことから、妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則が創設され、さらに免許の取消処分の対象に追加されました。
妨害運転(「あおり運転」)をした場合
(交通の危険のおそれ) |
罰則 |
違反点数 |
行政処分 |
| 他の車両等の通行を妨害する目的で、交通の危険を生じさせるおそれのある方法により「一定の違反」※をした場合 |
3年以下の懲役
または
50万円以下の罰金 |
25点 |
免許の取り消し(欠格期間2年)注1 |
注1 前歴や累積点数がある場合には欠格期間が最大5年に延長
妨害運転(「あおり運転」)により
著しい交通の危険を生じさせた場合 |
罰則 |
違反点数 |
行政処分 |
| 妨害運転(「あおり運転」)により、高速道路等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合 |
5年以下の懲役
または
100万円以下の罰金 |
35点 |
免許の取り消し(欠格期間3年)注2 |
注2 前歴や累積点数がある場合には欠格期間が最大10年に延長
※「一定の違反」妨害運転(「あおり運転」)の対象となる違反
- 通行区分違反
- 急ブレーキ禁止違反
- 車間距離の不保持
- 進路変更禁止違反(割込み)
- 追越しの方法違反
- 車両等の灯火違反(減光等)
- 警音器の使用等違反
- 安全運転義務違反
- 最低速度違反(高速道路)
- 高速道路等における駐停車違反
免許の仮停止処分の対象に追加
妨害運転(「あおり運転」)により交通事故を起こし人を死傷させた場合は免許の仮停止の対象となります。交通事故を起こした場所を管轄する警察署長等は、30日以内の範囲で免許の仮停止をすることができることとなりました。
自転車の「あおり運転」を危険行為として規定(道路交通法施行令)
他の車両を妨害する目的で執拗にベルを鳴らす、不必要な急ブレーキをかけるなど、自転車の「あおり運転」を危険な違反行為と規定します。3年間に2回違反した14歳以上の者は都道府県公安委員会により「自転車運転者講習」の受講が義務づけられます。
|

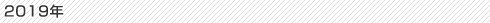

●
|
2019年12月1日施行
携帯電話使用等対策の推進を図るための規定の整備
車で走行しながらスマートフォンや携帯電話を使用したり、カーナビゲーションなどの画面を注視する「ながら運転」が厳罰化されました。違反点数・反則金などは約3倍と大幅に引き上げられ、事故など交通の危険に結びついた場合は、即免許停止になります。
携帯電話使用等により交通の危険を生じさせた場合
|
改正前 |
改正後 |
| 罰則 |
3月以下の懲役または
5万円以下の罰金 |
1年以下の懲役または
30万円以下の罰金 |
| 違反点数 |
2点(酒気帯び点数14点) |
6点(即免許停止)
(酒気帯び点数16点─取消) |
| 反則金 |
大型 |
1万2千円 |
非反則行為となり、
すべて罰則を適用 |
| 普通 |
9千円 |
| 二輪 |
7千円 |
| 小特等 |
6千円 |
※交通の危険とは、携帯電話等の使用により道路における交通の危険を生じさせたものをいいます。
携帯電話の使用等(保持)
|
改正前 |
改正後 |
| 罰則 |
5万円以下の罰金 |
6月以下の懲役または
10万円以下の罰金 |
| 違反点数 |
1点(酒気帯び点数14点) |
3点
(酒気帯び点数15点─取消) |
| 反則金 |
大型 |
7千円 |
2万5千円 |
| 普通 |
6千円 |
1万8千円 |
| 二輪 |
6千円 |
1万5千円 |
| 小特等 |
5千円 |
1万2千円 |
※保持とは、携帯電話等を使用し、または手に保持して画像を表示して注視したものをいいます。
運転免許の仮停止の対象行為に追加
携帯電話使用等(交通の危険)の違反をして、交通事故を起こして人を死傷させた場合、免許の効力の仮停止の対象となりました。これにより、交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、30日以内の範囲で免許の効力を停止(仮停止)することができます。
運転免許証の再交付要件の緩和
運転免許証の紛失、汚損、破損に加え、氏名変更や住所変更でも運転免許証の再交付の申請が可能となりました。
運転経歴証明書の交付要件の見直し等
自主返納者のみに限らず、免許失効者(運転免許証の更新を受けずに運転免許が失効した人)についても運転経歴証明書の交付申請が可能となりました。また、運転経歴証明書の申請先が、申請による運転免許の取消しを行った都道府県公安委員会から住所地の都道府県公安委員会に改められました。
|

| 
|

