
ラヴィ教習所がお届けする、交通安全にまつわるコラムです。
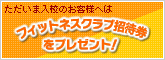
入校のお客様はラヴィセントラルフィットネスクラブ蒲田の招待券をプレゼント!
|

|



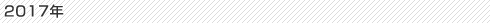

●
|
2017年3月12日施行
高齢者運転者対策の推進を図るための規定の整備
高齢者による交通事故を防止するため、認知症などに対する対策が強化されました。
(1)臨時認知機能検査・臨時高齢者講習の新設
・臨時認知機能検査
75歳以上の運転者が、認知機能が低下したときに起こしやすい一定の違反行為(18基準行為)をしたときには、臨時の認知機能検査を受けなければなりません。
【参考】違反行為(18基準行為)
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.通行区分違反
4.交差点右左折方法違反
5.横断等禁止違反
6.進路変更禁止違反
7.しゃ断踏切立入り等
8.指定通行区分違反
9.環状交差点左折等方法違反
10.優先道路通行者妨害等
11.交差点優先車妨害
12.環状交差点通行車妨害等
13.横断歩道等における横断歩行者等妨害等
14.横断歩道のない交差点における横断歩行者等妨害等
15.徐行場所違反
16.指定場所一時不停止違反
17.合図不履行
18.安全運転義務違反
・臨時講習者講習
臨時認知機能検査を受け、認知機能の低下が運転に影響するおそれがあると判断された高齢者は、「臨時高齢者講習」(実車指導と個別指導)を受けなければなりません。
(2)臨時適性検査制度の見直し
更新時の認知機能検査または臨時認知機能検査で「認知症の恐れがある」と判定された方は、「臨時適性検査」(医師の診断)を受け、または、命令に従い主治医等の診断書を提出しなければなりません。
※医師の診断の結果、認知症と判断された場合は、運転免許の取消しまたは停止となります。
(3)高齢者講習の合理化・高度化
高齢者講習は、75歳未満の方については2時間に合理化(短縮)されます。また、75歳以上の方については、認知機能検査の結果に基づいて、より高度化または合理化が図られた高齢者講習が実施されます。
免許更新時以外の講習の流れ(75歳以上)
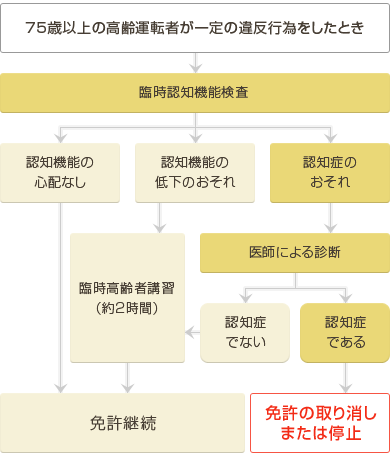
高齢運転者(70歳以上)の運転免許更新手続き
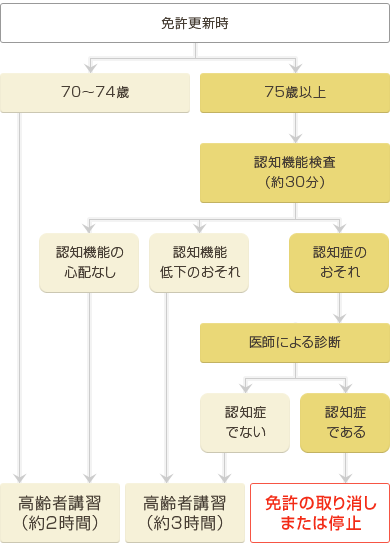
準中型免許の新設
準中型免許では、車両総重量7.5トン未満(最大積載量4.5トン)の自動車を運転できます(普通自動車も運転できます)。
普通免許で運転できる自動車は車両総重量3.5トン未満(最大積載量2トン未満)となります。
(1)準中型免許の受験資格・教習日数
準中型免許は、18歳から普通免許なしでも取得できます。教習では、最短17日で取得可能です。
【参考】普通免許は最短15日で取得可能!
(2)準中型免許に係る初心運転者期間制度
初めて準中型免許を取得した方は、準中型自動車を運転するときには1年間初心者マークをつけなければなりません。
(3)すでに普通免許を保有している方は
引き続き車両総重量5トン未満の自動車を運転することができます。さらに限定解除審査(※)に合格すれば、車両総重量5トン以上7.5トン未満の自動車の運転も可能になります。
※審査は、指定自動車教習所で最低4時間の教習等を受けた上での審査または運転免許試験場での技術審査等のいずれかになります。
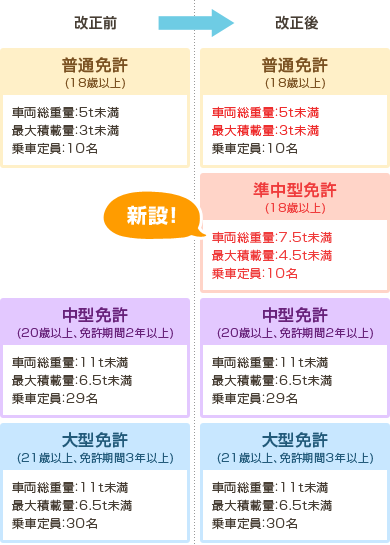
※2007年6月1日から2017年3月11日までに取得した普通免許の場合
車両総重量5t未満・最大積載量3t未満・乗車定員10名以下の車まで運転可能。
※2007年6月1日までに取得した普通免許の場合
車両総重量8t未満・最大積載量5t未満・乗車定員10名以下の車まで運転可能。
|

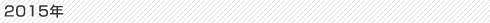

●
|
2015年6月17日施行
運転免許の仮停止の対象範囲の拡大
酒気帯び運転や過労運転等で交通事故を起こして人を傷つけた場合も、運転免許の仮停止の対象となりました。
| |
改正前 |
| 違反行為 |
交通事故の程度 |
| 死亡 |
傷害 |
| 救護義務違反(ひき逃げ) |
○ |
○ |
| 酒酔い運転 |
○ |
○ |
| 麻薬等運転 |
○ |
○ |
| 無免許運転 |
○ |
○ |
| 大型自動車等無資格運転 |
○ |
○ |
| 過労運転等(麻薬等運転を除く) |
○ |
- |
| 酒気帯び運転(0.15以上) |
○ |
- |
| 最高速度違反 |
○ |
- |
| 積載物重量制限超過 |
○ |
- |
| 信号無視 |
○ |
- |
| 追越し違反 |
○ |
- |
| 徐行義務違反 |
○ |
- |
|
 |
改正後 |
| 交通事故の程度 |
| 死亡 |
傷害 |
| ○ |
○ |
| ○ |
○ |
| ○ |
○ |
| ○ |
○ |
| ○ |
○ |
| ○ |
○ |
| ○ |
○ |
| ○ |
- |
| ○ |
- |
| ○ |
- |
| ○ |
- |
| ○ |
- |
|
|
| 
|
●
|
2015年6月1日施行
自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備
自転車の運転に関して一定の危険な違反行為を3年以内に2回以上繰り返す自転車運転者(悪質自転車運転者)に対して、自転車運転者講習(講習時間3時間・講習手数料5,700円)の受講を義務づけることになりました。公安委員会の受講命令を受けた自転車運転者は3カ月以内の指定された期間内に受講を受けなければなりません。受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金となります。
(参考)自転車による危険な違法行為
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
4.通行区分違反
5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害
6.遮断踏切立入り
7.交差点安全進行義務違反等
8.交差点優先車妨害等
9.環状交差点安全進行義務違反等
10.指定場所一時不停止等
11.歩道通行時の通行方向違反
12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
一定の病気等に該当すること等を理由として免許を取り消された場合における再取得した免許に係る免許証の有効期間に関する整備
一定の病気に該当すること等を理由に免許を取り消された場合、取消しから3年以内で免許を再取得した場合は、取り消された免許を受けた日から取り消された日までの期間と再取得した免許を受けていた期間は継続されていたものとみなされます。また、合計期間が5年以上で無事故・無違反であれば「優良運転者」となります。
|
| 
|
●
|
2015年4月1日施行
運転免許等に関する手数料の標準の改正
運転免許等に関する手数料の標準が改正されました。改正された主な手数料は以下の通り。
| |
改正前 |
| 優良運転者講習 |
更新手数料 |
2,500円 |
| 講習手数料 |
600円 |
| 合計 |
3,100円 |
| 一般運転者講習 |
更新手数料 |
2,500円 |
| 講習手数料 |
950円 |
| 合計 |
3,450円 |
| 違反運転者講習 |
更新手数料 |
2,500円 |
| 講習手数料 |
1,500円 |
| 合計 |
4,000円 |
| 初回更新者講習 |
更新手数料 |
2,500円 |
| 講習手数料 |
1,500円 |
| 合計 |
4,000円 |
|
 |
改正後 |
| 2,500円 |
| 500円 |
| 3,000円 |
| 2,500円 |
| 800円 |
| 3,300円 |
| 2,500円 |
| 1,350円 |
| 3,850円 |
| 2,500円 |
| 1,350円 |
| 3,850円 |
|
※その他、試験手数料なども改正されました。
|

|

|

